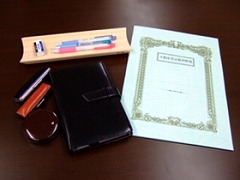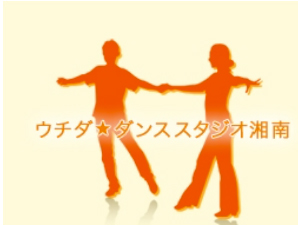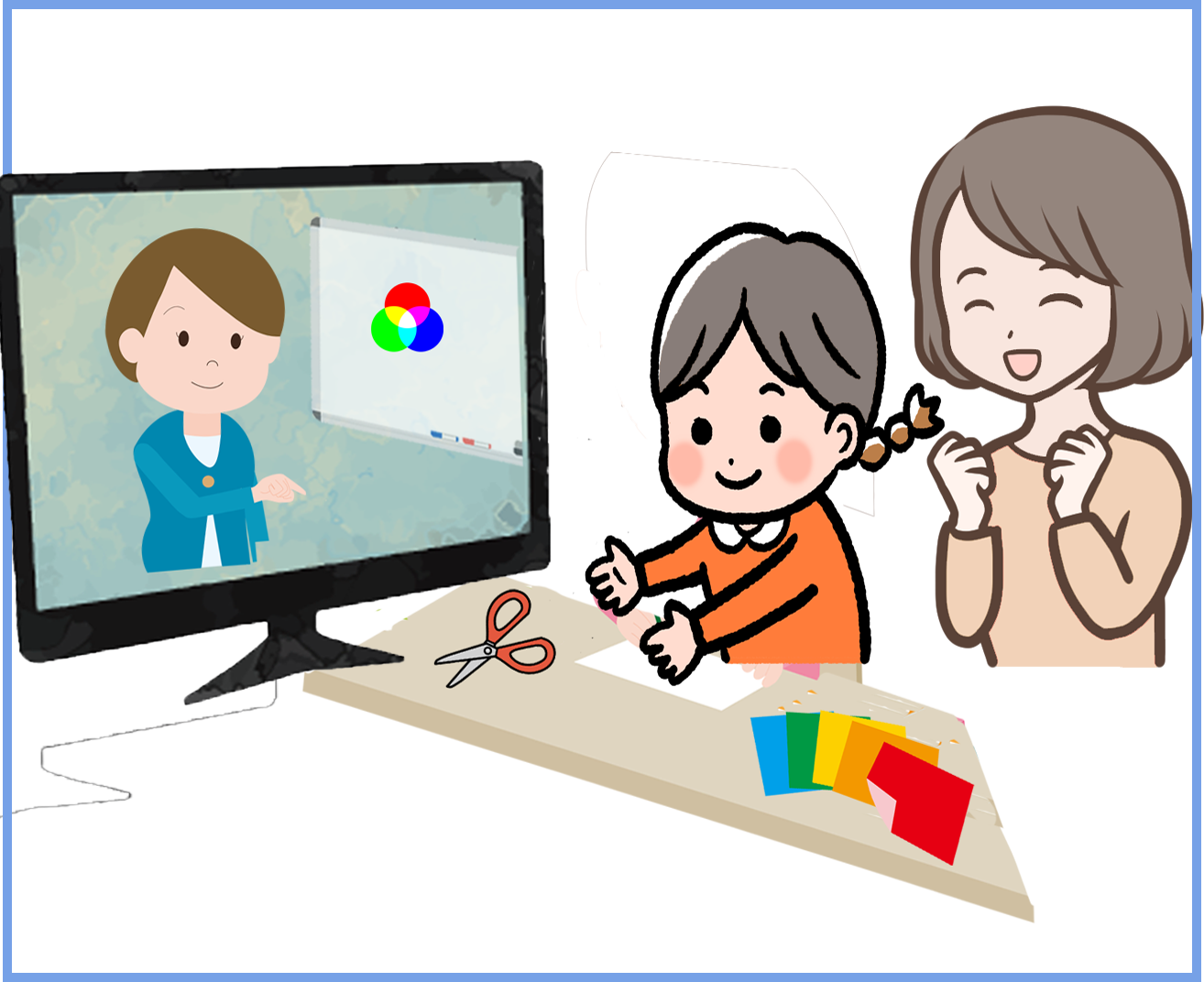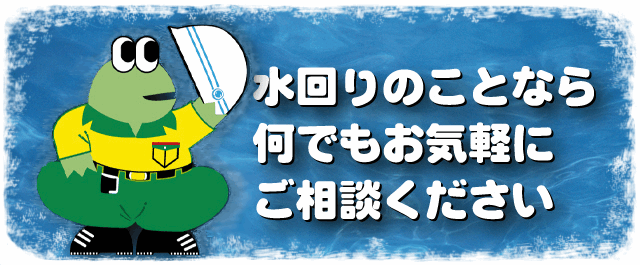江の島の植物・樹木≪アオキ≫≫
アオキは日本原産で、北海道南部から本州、四国、九州、沖縄に分布し、山野の林の中に自生する常緑の低木です。単性花で雌雄異株。江の島の海側の藪の中や参道脇、広場、龍野ヶ岡などに生育していますが、植栽されたものも多く、斑入りの葉をもつ園芸品種もあります。アオキは日陰でもよく育ち、年中青々と美しい葉を保つことから庭園や公園の植え込みに植栽され、観葉植物としても人気があります。雪の中で見るアオキの青葉と赤い実のコントラストは実に美しく、風情があります。アオキの仲間で変種のヒメアオキ・姫青木(var. borealis )は、北海道南部から本州の日本海側に分布していますが、アオキにくらべて全体に小形であり、積雪にも耐えられるようにしなやかで強靭です。
 アオキは茎先に紫褐色の小花を円錐花序に多数付ける(龍野丘で)
アオキは茎先に紫褐色の小花を円錐花序に多数付ける(龍野丘で) アオキの果実は約1.5㌢の楕円形で、秋に赤く熟し、翌年の4月頃まで残りますが、ヒメアオキに比較して大形で果実も多くつきます。
アオキの果実は約1.5㌢の楕円形で、秋に赤く熟し、翌年の4月頃まで残りますが、ヒメアオキに比較して大形で果実も多くつきます。アオキは耐寒性があり日陰でもよく育ち、低木であることから庭木としても利用されていますが、園芸種も多く、斑入り品種などは江戸時代にすでにつくられていたとされています。和名は枝・葉ともに年中緑色(青色)であることに因みます。アオキをヨーロッパに初めて紹介したのはドイツの外科医ケンベル(1690)で、学名Aucubaはアオキバ(青木葉)に由来します。アオキの葉を乾燥させたり、押し葉にしたりすると黒くなりますが、これは葉に含まれるアウクビゲニン(Aucubigenin)の酸化によるものです。この成分には抗菌作用があり、アオキは民間療法として古くから火傷や腫れものなどに用いられてきました。私も子供の頃は山や川でよく遊びましたが、木から落ちたり転んだりで怪我は絶えませんでした。そんなときアオキの葉を火であぶり、柔らかくなった熱い葉を患部に貼ってもらったことを思い出します。

長野県白馬村の山中に生えるヒメアオキです。全体に小形で高さは約70㌢でした。
(撮影H23 .4.30)


 アオキは日本原産で、北海道南部から本州、四国、九州、沖縄に分布し、山野の林の中に自生する常緑の低木です。
アオキは日本原産で、北海道南部から本州、四国、九州、沖縄に分布し、山野の林の中に自生する常緑の低木です。