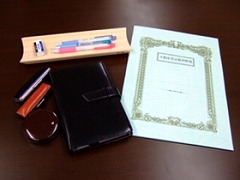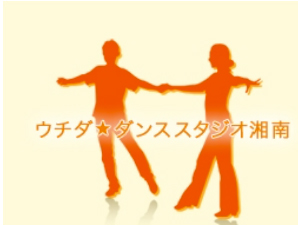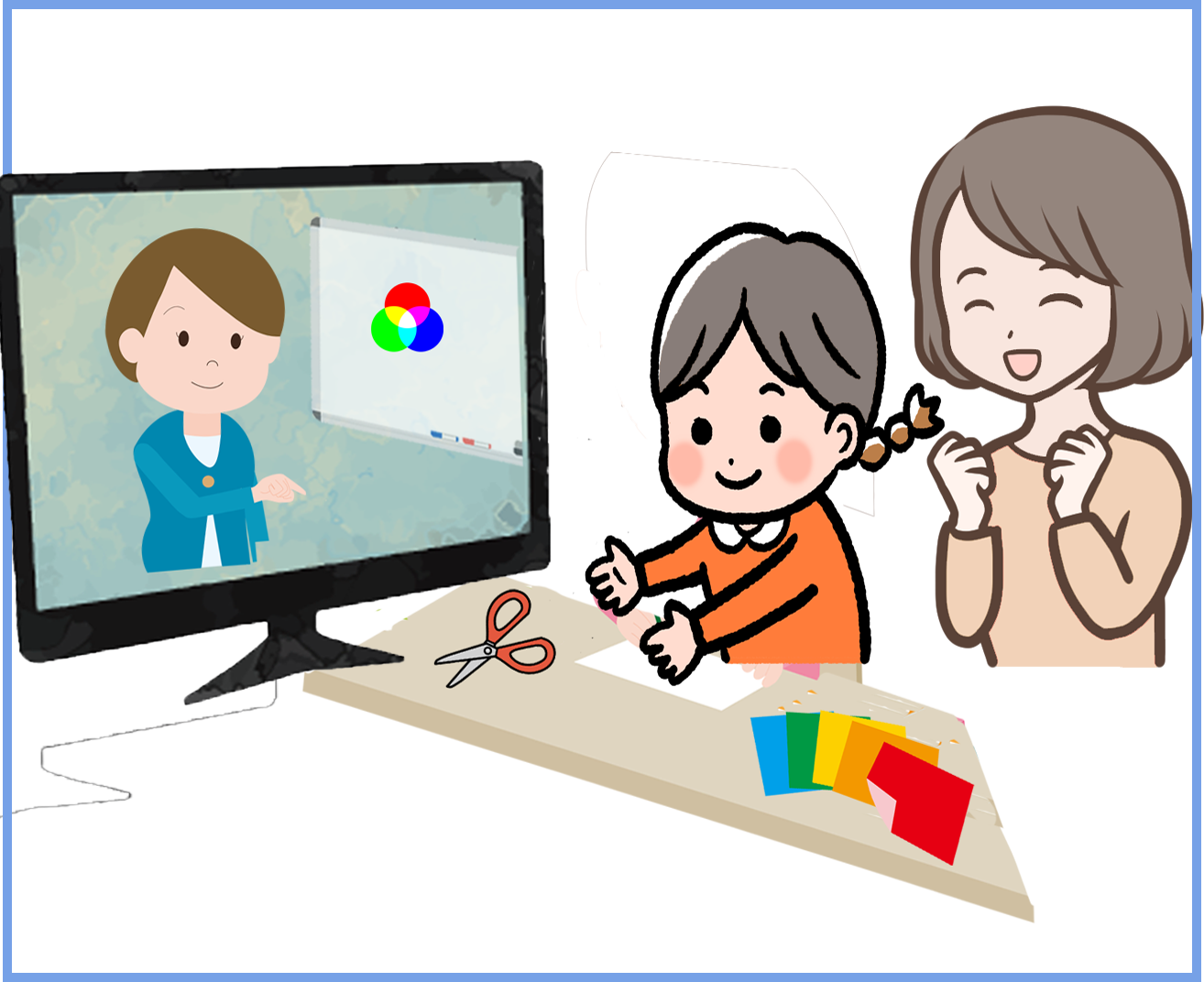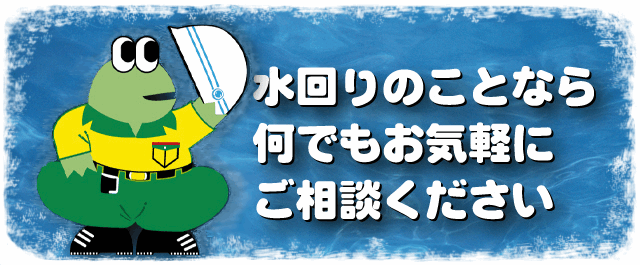江の島に咲く花≪ハマダイコン≫ ハマダイコンは海岸の砂地に生える多年草で、春を告げる花として海辺を美しく彩ります。そのさや(莢)は丈夫なコルク質で、熟すと軽くなり海流にのって他の海岸へ漂着しそこで発芽して、日本列島全域に分布していったものと考えられています。
ハマダイコンは海岸の砂地に生える多年草で、春を告げる花として海辺を美しく彩ります。そのさや(莢)は丈夫なコルク質で、熟すと軽くなり海流にのって他の海岸へ漂着しそこで発芽して、日本列島全域に分布していったものと考えられています。
ハマダイコン(浜大根)Raphanus sativus var. raphanistroides |
| ハマダイコンは海岸の砂地に生える多年草で、春を告げる花として海辺を美しく彩ります。そのさや(莢)は丈夫なコルク質で、熟すと軽くなり海流にのって他の海岸へ漂着しそこで発芽して、日本列島全域に分布していったものと考えられています。 写真は江の島ガーデンパーラーの海側斜面に群生しているハマダイコンですが、さらに進んで岩屋へ向かう海側斜面などの処々でその生育が見られます。 従来、ハマダイコンは食用ダイコンが野生化したものであるとされてきましたが、疑問視する意見もあり、その起源についてさらなる検討が待たれます。生育環境は海岸 花期は3~5月 |
 ガーデンパーラーの海側斜面に咲くハマダイコン |
| ダイコンは地中海沿岸を起源とし、中国を経て弥生時代には日本に渡来していたと考えられています。特に江戸時代以降において、その栽培技術や品種改良が進み、日本各地にそれぞれの特徴をもつ多くの在来品種が生まれました。 食用ダイコンを古くは「オオネ(大根)」または「オホネ(於朋泥)」と呼び、古事記や日本書紀にその記載がありますが、一方「スズシロ」とも呼ばれ、源氏物語の注釈書を著した四辻善成著(1362~1367)の「河海抄」に『せりなずな ごぎょうはくべら ほとけのざ すずなすずしろ これぞ七草』と詠まれており、すずしろ(ダイコン)は春の七草のひとつになっています。これがダイコンと呼ばれるようになったのは室町時代(1392~1573)からといわれています。 |
  海辺に咲くハマダイコン と ハマダイコンの花 |
| ハマダイコンの茎の高さは30~70cmで枝を分け、葉は根本から束生して葉柄は太く水平に開き、葉の長さは4~20cm、羽状に分裂し粗い毛があります。 江の島では3月下旬に開花し、茎の先に総状花序を出して淡紅紫色の花を開きます。萼片は4個で直立し淡緑色、花弁4枚が十字状に開き、倒卵形で先はへこみ、その基部は長い楔形で長さは約2 cm、紫の筋があります。 長角果は円柱形で数珠状にくびれ長さは5~8cm、中に2~5個の種子を包み、熟しても開裂しません。 和名の由来は海岸(浜)に生える大根でハマダイコン(浜大根)、ダイコンは大きな根をもつことに因みます。 |
【写真&文:坪倉 兌雄 2011-01-22】 |