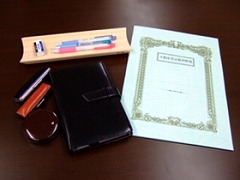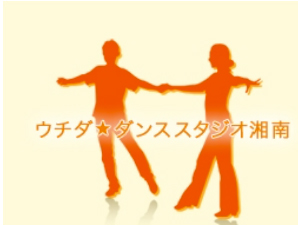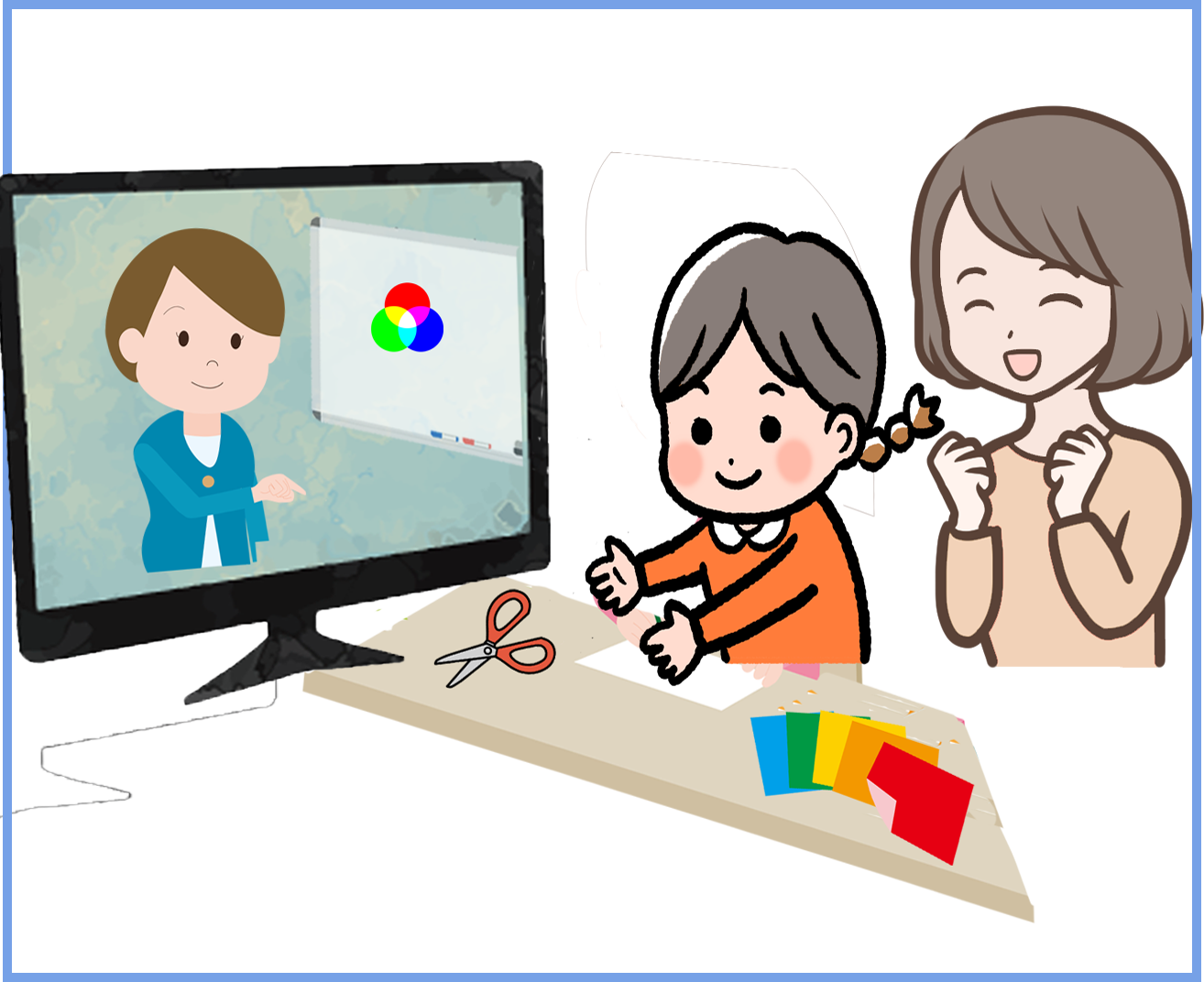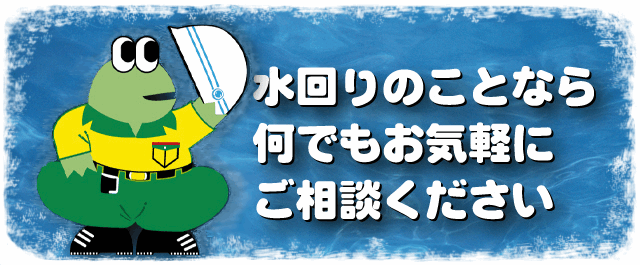江の島に咲く花≪キケマン≫  キケマンは海岸や低地に生える越年草で、花は美しいのですが、近寄ると悪臭があります。本草は関東地方以西の四国、九州、沖縄に分布し、江の島では参道傍や西浦漁港付近の山側などに生育しています。
キケマンは海岸や低地に生える越年草で、花は美しいのですが、近寄ると悪臭があります。本草は関東地方以西の四国、九州、沖縄に分布し、江の島では参道傍や西浦漁港付近の山側などに生育しています。
キケマン(黄華鬘)Corydalis heterocarpa var.japonica |
| キケマンは海岸や低地に生える越年草で、花は美しいのですが、近寄ると悪臭があります。本草は関東地方以西の四国、九州、沖縄に分布し、江の島では参道傍や西浦漁港付近の山側などに生育しています。茎や葉を傷つけると黄色の液体が出て悪臭を放ちますが、全草にアルカロイド系の有毒成分を含み、食べると嘔吐、眠気、呼吸麻痺、心臓麻痺などの症状を呈するといわれています。生育地は海岸や低地 花期は4~6月 |
 江の島の路傍に咲くキケマン |
| 近縁種にはムラサキケマン、ミヤマケマン、ツルケマンなどがあり、いずれも有毒植物ですが、ミヤマケマンとツルケマンは江の島には自生していません。また観賞用として人気があるケマンソウ(コマクサ属)にも有毒成分があります。 キケマンは比較的日当たりのよい場所に生育しますが、ムラサキケマン(紫華鬘)は江の島のやや湿ったところに生え、開花時期はキケマンとほぼ同じです。 和名の由来は花が黄色で、仏前を飾る華鬘(ケマン)に似ることからキケマン(黄華鬘)で、ムラサキケマンは同じケマンソウの仲間で花が紫色であることに因みます。 ケマン(華鬘)とは仏前を荘厳にするために内陣の欄間などにかける装飾具のことをいい、もとはインドの風俗で身体を装飾するために用いた花輪などが、転じて仏具になったものとされています。 |
  江の島に咲くムラサキケマン キケマンの葉と花 |
| キケマンの茎は太く高さ40~80cm、根本から枝を分けて大きな葉をだし、葉の長さは約20cm、白緑色で3~4回羽状に裂けます。花期は4~6月、茎の先に長い総状花序をだし長さ1.5~2cmの黄色い花を茎に沿って縦長につけます。蒴果は狭い披針形で長さは約7.5cmです。仲間のムラサキケマンの葉は2~3回羽状に細かく裂け、裂片はさらに切れ込みます。花は茎の上部に総状につき、長さ1.2~1.8cm、先は唇形となり、花の先端部は紅紫色を呈します。 ケシ科コマクサ属のケマンソウは、中国原産の多年草で、観賞用として植栽されますが、アーチ状に曲がった茎に淡紅色の美しいハート型の花を吊り下げるので、別名をタイツリソウ(鯛吊草)とも呼ばれています。 |
【写真&文:坪倉 兌雄 2011-03-05】 |