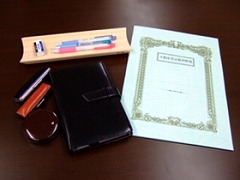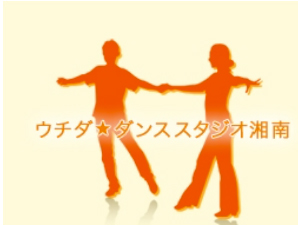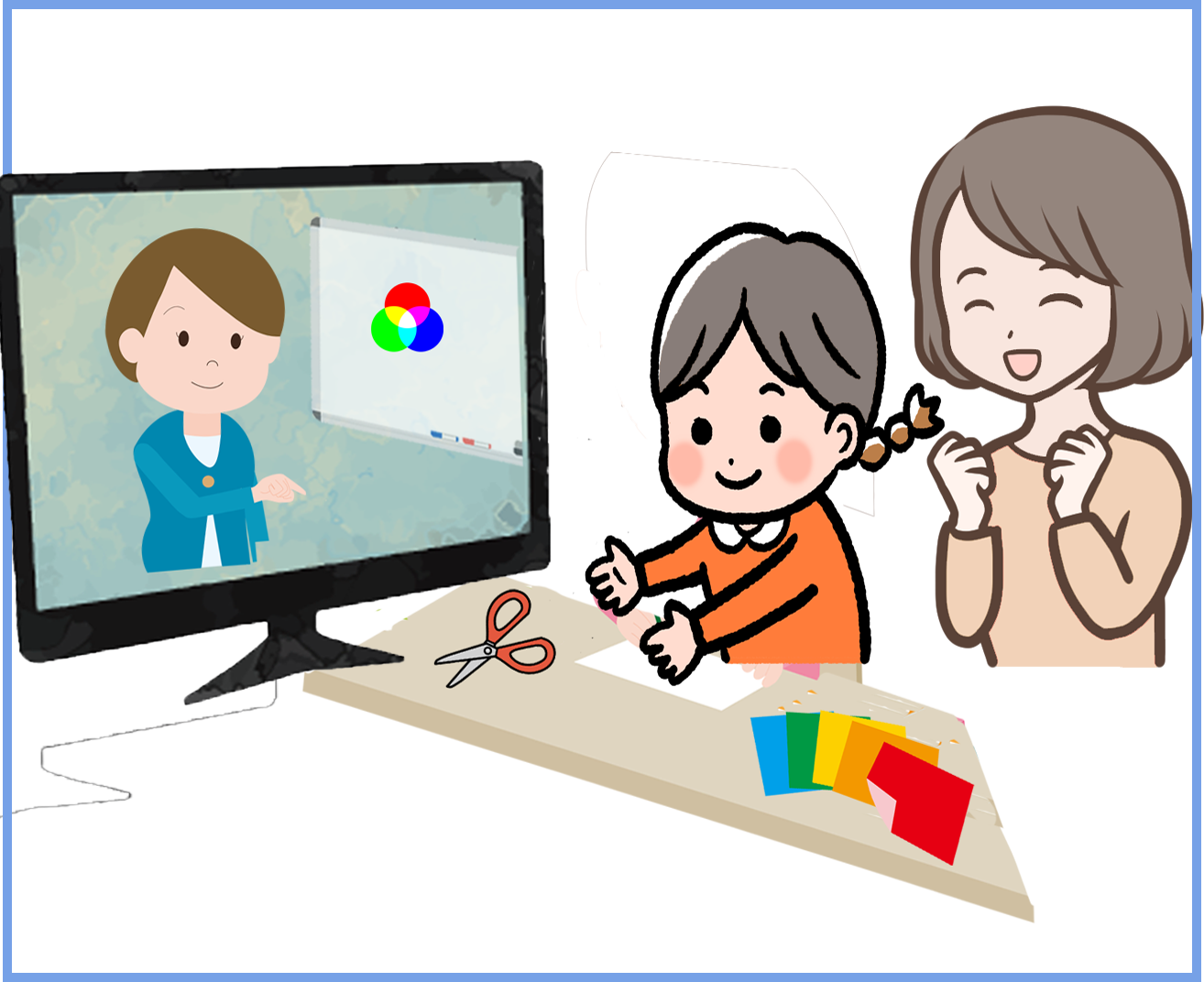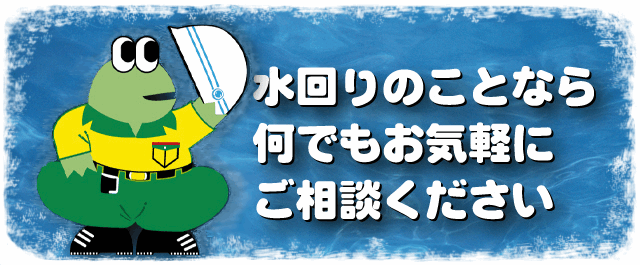江の島に咲く花≪ヒゲスゲ≫ ヒゲスゲは本州の北陸、関東以西~沖縄に分布する常緑の多年草で、江の島では海辺の岩場や林中、かながわ女性センター裏側の石垣付近などに生育し、特に西浦漁港から稚児ヶ淵にかけての岩場では大株が見られ、冬場でもかたくて艶のある美しい葉を密生しています。
ヒゲスゲは本州の北陸、関東以西~沖縄に分布する常緑の多年草で、江の島では海辺の岩場や林中、かながわ女性センター裏側の石垣付近などに生育し、特に西浦漁港から稚児ヶ淵にかけての岩場では大株が見られ、冬場でもかたくて艶のある美しい葉を密生しています。
ヒゲスゲ(髭菅) Carex oahuensis var. robusta |
| ヒゲスゲは本州の北陸、関東以西~沖縄に分布する常緑の多年草で、江の島では海辺の岩場や林中、かながわ女性センター裏側の石垣付近などに生育し、特に西浦漁港から稚児ヶ淵にかけての岩場では大株が見られ、冬場でもかたくて艶のある美しい葉を密生しています。花期は比較的早く江の島では2月初旬から茎先に小穂を直立させた株を見ることができます。本種に良く似た仲間のカンスゲ(寒菅)も常緑の多年草で、江の島のやや湿ったところに自生していますが、ヒゲスゲに比べていくぶん小形であることから区別できます。 |
 江の島の海辺に生えるヒゲスゲ 江の島の海辺に生えるヒゲスゲ |
| スゲ(菅)はカヤツリグサ科スゲ属の総称でいずれも三角形または円形の茎をもち、かつては夏にその葉を刈り取り、笠(菅笠)、蓑(みの)、縄などを作る材料として用いられ、古事記に「須宣」、万葉集には「須気」または「菅」として登場し「かきつばた佐紀沼(咲き沼)の菅を笠に縫ひ着む日を待つに年ぞ経にける」とあり、江戸初期の流行唄『菅笠節』には「破れ菅笠やんやしめ緒が切れてのうえ・・」とも歌われています。日本一の生産量をもつ越中福岡の菅笠技術は400年以上の歴史をもち、その伝統技術は今に受け継がれています。 |
  雄蕊(頂穂)と雌蕊 及び (側小穂)側小穂鱗片の芒 |
| スゲ(菅)はカヤツリグサ科スゲ属の総称でいずれも三角形または円形の茎をもち、かつては夏にその葉を刈り取り、笠(菅笠)、蓑(みの)、縄などを作る材料として用いられ、古事記に「須宣」、万葉集には「須気」または「菅」として登場し「かきつばた佐紀沼(咲き沼)の菅を笠に縫ひ着む日を待つに年ぞ経にける」とあり、江戸初期の流行唄『菅笠節』には「破れ菅笠やんやしめ緒が切れてのうえ・・」とも歌われています。日本一の生産量をもつ越中福岡の菅笠技術は400年以上の歴史をもち、その伝統技術は今に受け継がれています。 |
【写真&文:坪倉 兌雄 2010-03-13】 |