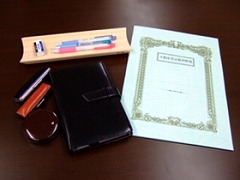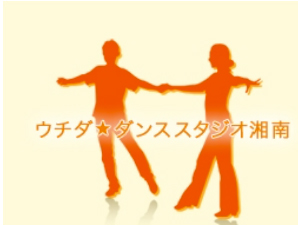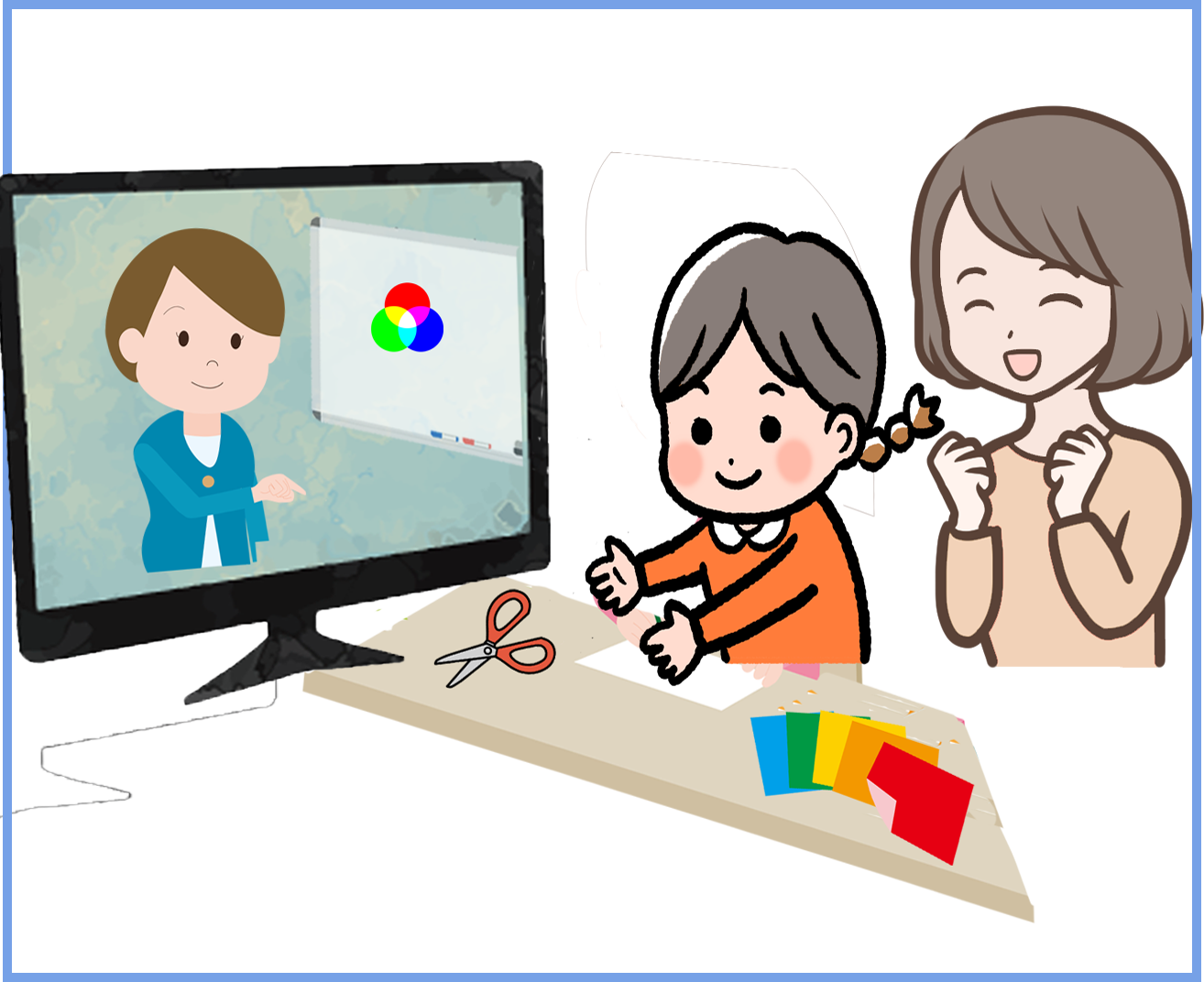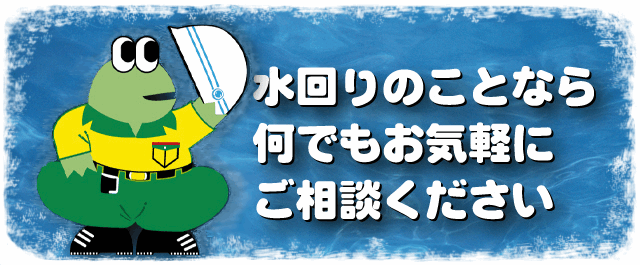江の島に咲く花≪タイトゴメ≫ タイトゴメは関東地方以西の本州~四国、九州、南西諸島に分布する小形の常緑多年草で、主に日当たりの良い岩場や崖などによく分岐して生育し、江の島では海側の岩場や崖などでその群生が見られ、
タイトゴメは関東地方以西の本州~四国、九州、南西諸島に分布する小形の常緑多年草で、主に日当たりの良い岩場や崖などによく分岐して生育し、江の島では海側の岩場や崖などでその群生が見られ、
タイトゴメ(大唐米) Sedum oryzifolium |
| タイトゴメは関東地方以西の本州~四国、九州、南西諸島に分布する小形の常緑多年草で、主に日当たりの良い岩場や崖などによく分岐して生育し、江の島では海側の岩場や崖などでその群生が見られ、また道路脇の日当たりの良い砂地や街路樹の下などでも観察できます。塩害や乾燥した岩場など厳しい環境の中で生き抜くために「CAM植物」特有の光合成を行っています。CAMはベンケイソウ型有機酸代謝(crasssulacean acid metabolisum) の略です。生育環境は海辺 花期は5~7月 |
 江の島の岩場に群生するタイトゴメ |
| 夜間に気孔を開き二酸化炭素を取り込み、リンゴ酸などの有機物にして液胞に蓄えておき光合成の際、二酸化炭素にもどして使う方法です。昼間は気孔を閉じた状態で光合成を行なえるので水分の蒸散を最小限に抑えることができるのです。さらに厳しい乾燥時期には自分自身の呼吸で作られた二酸化炭素も利用することができます。これらの性質を利用して、ビルの屋上緑化や乾燥した痩せ地などの緑化に、タイトゴメなどの「CAM植物」を利用することができます。ベンケイソウ科の他にサボテン科、トウダイグサ科などの多肉質の葉をもつ植物の一部にもCAM植物があります。 |
  群生したタイトゴメの花 |
| 夜間に気孔を開き二酸化炭素を取り込み、リンゴ酸などの有機物にして液胞に蓄えておき光合成の際、二酸化炭素にもどして使う方法です。昼間は気孔を閉じた状態で光合成を行なえるので水分の蒸散を最小限に抑えることができるのです。さらに厳しい乾燥時期には自分自身の呼吸で作られた二酸化炭素も利用することができます。これらの性質を利用して、ビルの屋上緑化や乾燥した痩せ地などの緑化に、タイトゴメなどの「CAM植物」を利用することができます。ベンケイソウ科の他にサボテン科、トウダイグサ科などの多肉質の葉をもつ植物の一部にもCAM植物があります。 |
【写真&文:坪倉 兌雄 2010-06-19】 |