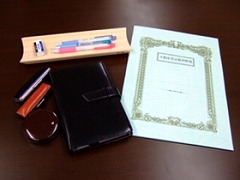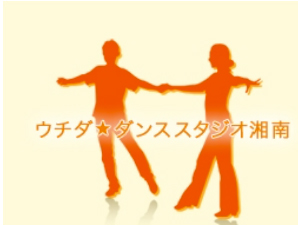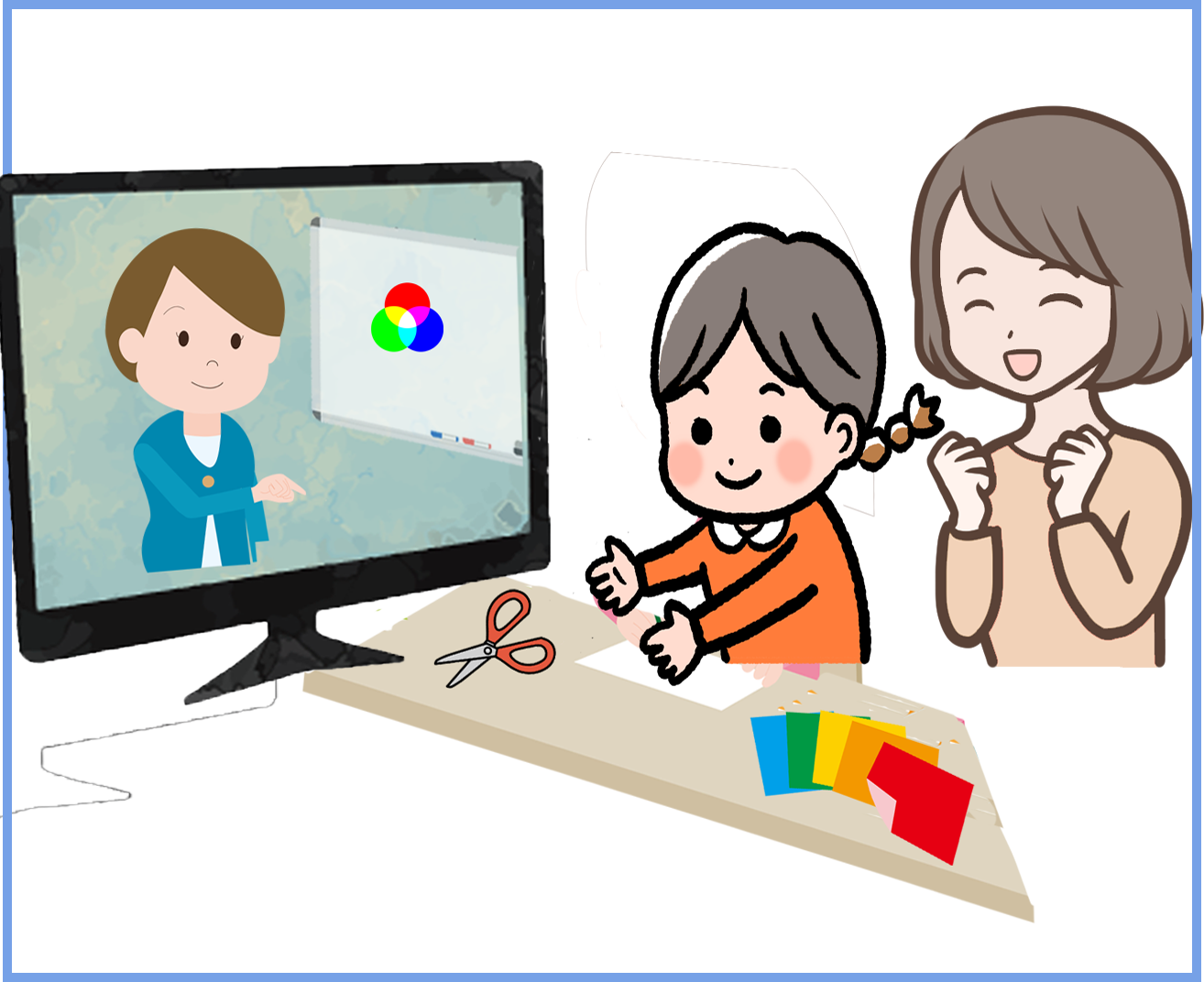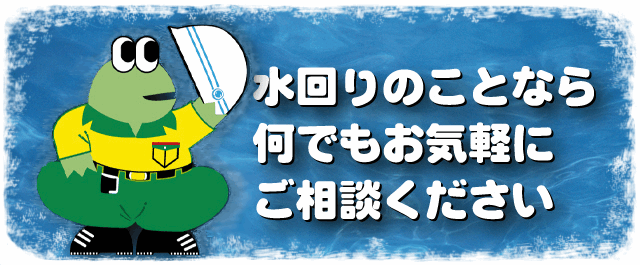ツルナ(蔓菜)ツルナ科 ツルナ属 多年草 花期 4~11月
ツルナ(蔓菜)ツルナ科 ツルナ属 多年草 花期 4~11月
ツルナは北海道西南部から本州~沖縄の太平洋側に分布する多年草で、江の島では海側の岩場や砂地、かながわ女性センター裏付近に生育しています。
ツルナ(蔓菜)Tetragonia tetragonoides |
| ツルナは北海道西南部から本州~沖縄の太平洋側に分布する多年草で、江の島では海側の岩場や砂地、かながわ女性センター裏付近に生育しています。 本草は江戸時代の貝原益軒著「大和本草」、小野欄山「大和本草会議」などに記載され、ハマナ(浜菜)とも呼ばれて食用や薬草として古くから用いられてきました。淡白で独特の風味があり、栄養価に富み、ビタミンやミネラルも豊富です。 |
 江の島の海辺に生えるツルナ |
| 英名はNew Zealand spinach(ニュージーランドホウレンソウ)で、海洋探検家キャプテンクック〈1772〉が、ニュージーランドから持ち帰り植栽したのが始まりとされ、欧米では栽培してホウレンソウと同じような調理法でサラダなどにも用いられています。本草には薬効成分があり、胃潰瘍や胃酸過多、胃炎などにも効果があるとされています。 |
|
茎の高さは40~60cm、よく枝分れして地表をはい蔓状になって生長します。葉は茎に互生し肉厚で無毛、三角卵形で軟らかく長さ4~6cm。茎と葉に粒状の突起があり、全体が白い粉をふいたように見えます。4~11月、葉のわきに小さな花をつけますが花弁は無く、萼が4~5裂して花弁状になり内側は黄色、外側は緑色を呈します。果実には3~5個の突起があり。黒く熟すと軽くなって風に舞い、海水に浮いて海の冒険に、そして漂着したところで発芽し繁殖します。かつては「浜ぢしゃ」とか「浜菜」と呼ばれていましたが、江戸時代になってから蔓菜と呼ばれるようになりました。 |
【写真&文:坪倉 兌雄 2009-11-07】 |