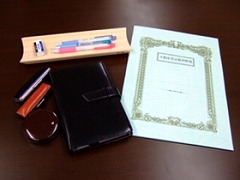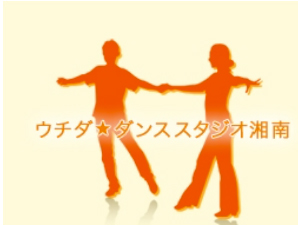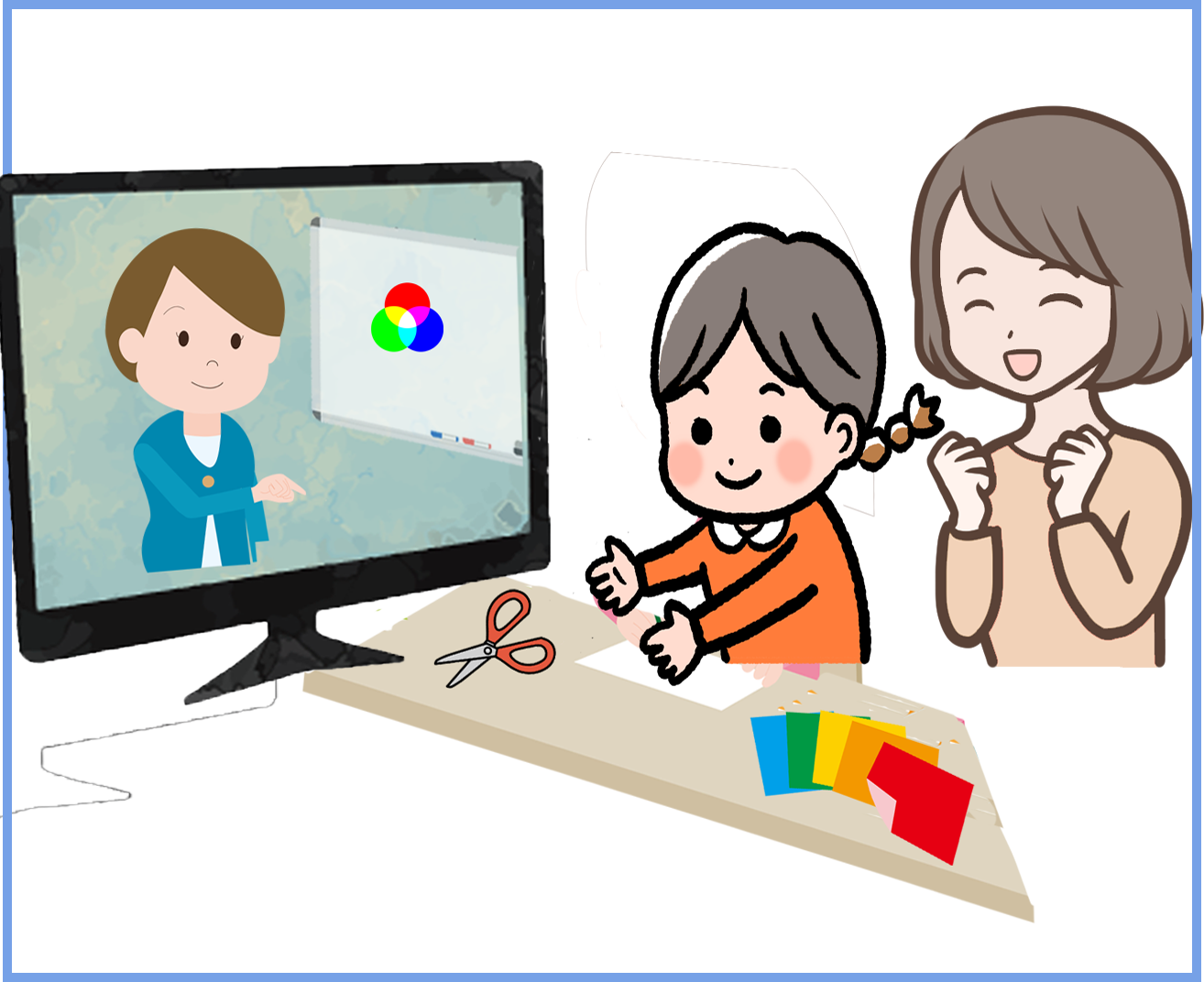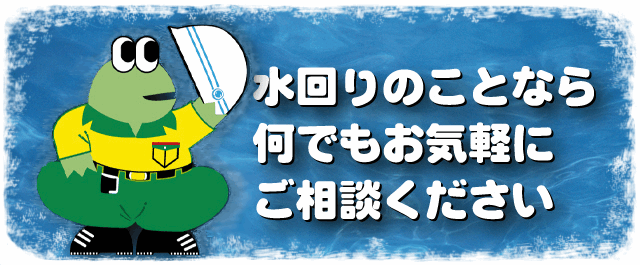歴史探訪52:鎌倉市十二所(じゅうにそ)の光触寺(こうそくじ)を訪ねる
2024年8月21日 ( itazu)
十二所は朝比奈切通の鎌倉側の出入口
十二所は、朝比奈切通しの鎌倉側の出入口にあたる場所で、朝比奈峠から下る滑川沿いに金沢街道が通っています。光触寺の近くに「十二所神社」があり、その前身は「熊野十二所権現社」だったところから、「十二所」の地名があるといわれます。


一遍上人が鎌倉へ来られた時、帰依して時宗に
今回訪ねた光触寺(こうそくじ)」は鎌倉時代(1278年)に創建された古刹です。
開山は作阿上人で、時宗の開祖・一遍上人が開基と伝えます。
作阿上人はもともと真言宗の僧でしたが、一遍上人が鎌倉へ遊行に来られた時、帰依して時宗に改めたといわれます。境内には、一遍上人の像があり、時宗の中でも遊行寺などより古い寺になります。

頬焼阿弥陀は重要文化財
光触寺には、重要文化財に指定されている本尊の木造阿弥陀如来および両脇侍立像(頬焼阿弥陀)があり、運慶作と伝えられます。盗みの疑いをかけられた法師の身代わりになり、阿弥陀仏の頬に焼印が残ったといわれる伝説があります。

(ウィキペディア「光触寺」より転載)

六浦から鎌倉への塩の道(塩嘗地蔵)
本堂の前の「塩嘗地蔵」は六浦の塩売りが、朝比奈峠を越えて鎌倉に来るたびにお地蔵様に塩をお供えしたといい、いつも帰りにはなくなっていたところからその名の由来があります。
昔は、六浦は塩の産地で、金沢方面から鎌倉へ塩が入ってきていました。
朝比奈三郎の滝は、朝比奈切通の鎌倉街道側の出入口
光触寺から、滑川の支流の大刀洗川沿いの山道を遡ると、朝比奈切通の鎌倉街道側入口に朝比奈三郎の滝壺があります。大刀洗川には、梶原景時が上総介広常を討った後、ここの湧き水で血刀を洗ったとされる「梶原大刀洗水」があり、武将をはじめ,商人など、この古道で鎌倉ー六浦との往来が行われていたことがわかります。




(参照資料:ウィキペディア、光触寺公式ホームページ、神奈川歴史探訪問ルートガイド(横浜歴史研究会)、鎌倉の寺社122を歩く(PHP新書)
記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。 ☑ 2024年8月21日