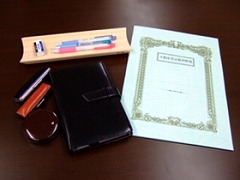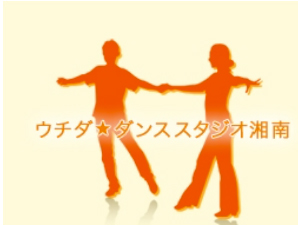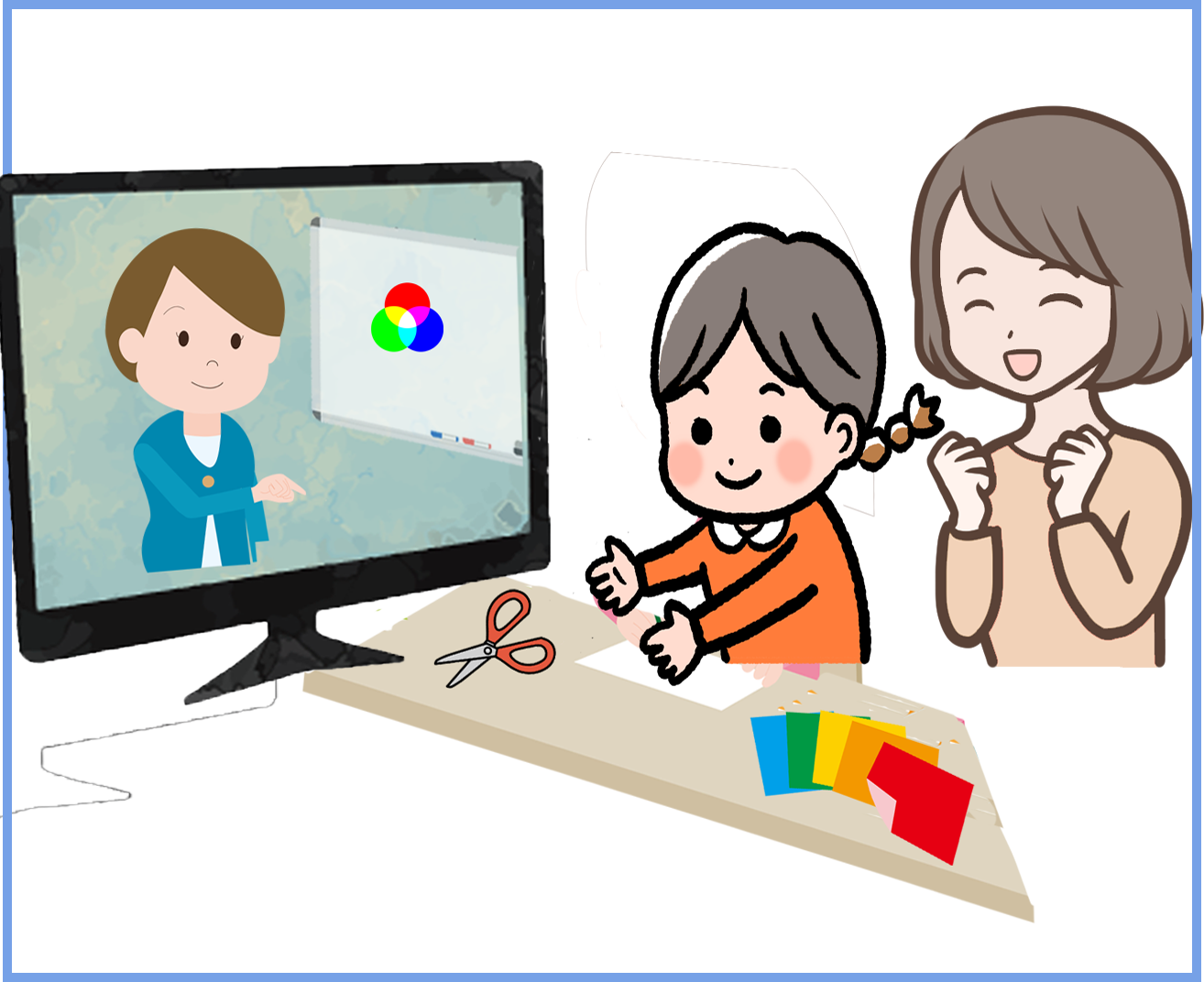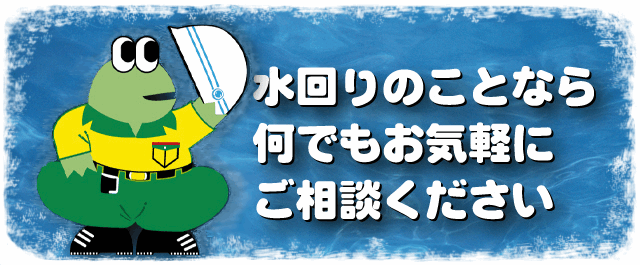歴史探訪27 北条政子ゆかりの安養院を訪ねます
歴史探訪27 北条政子ゆかりの安養院を訪ねます歴史探訪問(27) 北条政子ゆかりの安養院
安養院は鎌倉市大町にある浄土宗の寺院です。寺の案内によれば
「安養院は、北条政子が、頼朝の冥福を祈るために笹目ケ谷に建立した長楽寺が前身と伝えられている。その後、鎌倉時代末期に善導寺の跡(現在地)に移って安養院になった。安養院は北条政子の法名。1680年に全焼したため、頼朝に仕えていた田代信綱がかつて建立した田代寺の勘音堂を移し、「祇園山安養院田代寺」となった。」
とあります。

安養院本堂

安養院関連浄土宗寺院地図
安養院の前身の長楽寺の跡は、笹目ガ谷にあり、現在鎌倉文学館となっています。
鎌倉文学館の入口に長楽寺跡の石碑があります。
1225年に頼朝の冥福を祈るため創建された長楽寺は800m四方に七堂伽藍が建つ大寺院でしたが、1333年新田義貞の鎌倉攻めの戦火により焼失しました。このため、同じく焼失してしまった大町の善導寺跡地へ移され安養院となりました。

鎌倉文学館入口
注:長楽寺の跡地は、1891年前田家が入手し、1923年現在の洋風建築が建てられ、戦後は佐藤栄作首相の別荘になり1985年以降は鎌倉文学館。
→右は長楽寺址の石碑

善導寺の開山は尊観、北条政子の墓がある
善導寺は、長楽寺と併合して安養寺となりましたので、この地には、善導寺を開山した尊観のものと伝えられる宝篋印塔(ほうきょういんとう:墓碑塔のこと)(写真右)が、北条政子の墓(写真左)と共に残されています。国の重要文化財です。

北条政子の墓

尊観のものと伝えられる宝篋印塔。国の重要文化財です。

安養院に残されている尊観が植えたとされる槇の巨木
浄土宗を関東への布教を始めたのは、三祖良忠とその弟子尊観
尊観は、北条(名越)朝時(なごえ_ともとき)の子で、義時の孫にあたります。
鎌倉幕府が開かれ ,都市化と共に成長する商人や住人を布教の対象に新たな宗教、浄土宗、法華経、禅宗、律宗などが入ってきていますが、その先頭を切ったのが浄土宗の念仏者でした。
浄土宗の関東への布教を始めたのは、三祖良忠とその弟子尊観です。尊観の北条氏の一門の名越氏をバックに 長楽寺(1225年)、光明寺(1244年良忠開山)、善導寺(時期不明、尊観開山)、大仏殿(1252年)など浄土宗の寺院が建てられてゆきます。
頼朝は、東大寺の仏像再建や善光寺の再建を支援してきていますが、阿弥陀仏が、八幡神社の本地仏(本来の姿)と考えられてきており、以来、北条泰時の時代には、鶴岡八幡宮と鎌倉大仏を鎌倉の発展の宗教的な支柱にして展開されてきました。(その後の北条時頼以降の鎌倉は、禅宗が主流となってゆきます。)
{参照資料:日本の中世7 中央公論新社(五味文彦著)、ウィキペディア他}